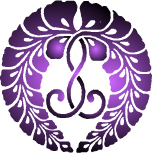念仏とジャイ・ビーム ― 仏教の平等の精神
仏教はお互いに尊重し合うことを勧める教えです。それは「誰もが平等であり、上下の差はない」という仏さま方に共通する精神でもあります。
おしゃか様が誕生されたとき、「天上天下唯我独尊」と言われたと伝えられています。これは、「すべての人は仏となる可能性を持ち、等しく尊ばれる存在である」という意味があり、ここに仏さまの平等の精神が表れています。
浄土真宗では、この精神は阿弥陀仏の本願に表されていて、それは、すべての人に平穏と安心を与えようとする願いです。阿弥陀仏の大いなる慈悲は、すべての人を差別なく包み込んでくださっていて、「南無阿弥陀仏」とは、その慈悲をいただいた私が、「阿弥陀仏に帰依します」という意味になります。私たちが念仏を称えるとき、阿弥陀仏の慈悲の願いと共に平等の精神も受け取るので、自分もできるだけ他の人々を尊重し、思いやりを持とう、という心が育まれるようになっています。
約2500年前、お釈迦さまの教団では、カースト制度をなくしました。お釈迦さまは皆が平等なコミュニティを教団の中だけでなく社会全体にも広げられることを望んでいたのかどうかは分かっていません。後に、インドで仏教が盛んになっても社会ではカースト制度が続きましたが、お釈迦様の平等の精神は何世紀にもわたって人々に影響を与えました。けれども、13世紀頃に仏教がインドで衰退するころには、その影響も薄れていました。
1950年代、ダリット出身の指導者であるB.R.アンベードカル博士は、平等を求める運動を率いました。彼はカースト制度の最下層に生まれ、多くの苦難を乗り越えてインド初の法務大臣となりました。1947年にはインド憲法の草案作成に携わり、カースト制度の廃止に尽力しました。そして1950年、カースト制度は公式に廃止されました。1956年、アンベードカル博士は50万人の支持者とともに仏教に改宗し、仏教を平等と尊厳への道としました。これがインドにおける新仏教運動(ネオ・ブディズム)の始まりでした。
アンベードカル博士が亡くなった後も、その影響は強く残っています。インドの多くの仏教徒は、「ジャイ・ビーム」(「ビームラーオ・アンベードカル万歳!」)という挨拶を交わします。この言葉は、平等と人間の尊厳の勝利を象徴しています。ネオブッディストにとって、「ジャイ・ビーム」と唱えることは、アンベードカル博士の精神を思い出し、差別のない社会を築く努力を続けることを意味しています。
1960年代後半、日本の僧侶である佐々井秀嶺師はインドへ渡りました。師はかつて人生に苦しみましたが、仏教によって新たな生き方を見出しました。インドに着いたとき、アンベードカル博士のことを知り、平等な社会を作るという彼の使命に深く感動しました。そして、佐々井師はインドに留まり、ダリットの人々に仏教を広めることを決意しました。
インドでの活動を始めたばかりの頃、佐々井師はある仏教集会で話す機会を得ました。しかし、当時は現地の言葉が話せず、何を言えばよいか分からなかったので、自分が知っている言葉、「ジャイ・ビーム」と言おうと決めました。20万人の群衆を目の前にして、佐々井師は「ジャイ・ビーム!」と三回叫びました。最初、会場は静まり返りました。しかし、次の瞬間、20万人もの人々が「ジャイ・ビーム!ジャイ・ビーム!」と大きな声で応えました。その瞬間から、佐々井師は人々に受け入れられ、ネオブッディスト運動の支援に生涯を捧げることになりました。何年にもわたり、数百万人に仏教を伝え、平等と尊敬の精神を広め続けてきました。現在も佐々井師は活動を続けておられます。
「南無阿弥陀仏」と「ジャイ・ビーム」には共通する精神があります。両方とも平等を伝える言葉です。「南無阿弥陀仏」は、阿弥陀仏の限りない慈悲がすべての人を平等に包み込むことを表現し、「ジャイ・ビーム」も、アンベードカル博士が築いた平等の精神を表現しています。
私たちが「南無阿弥陀仏」と称えるとき、すべての人の平和と安心を願う心を阿弥陀さまからいただいています。この平等の精神を心に抱き、日々の生活の中でできるだけ実践していきましょう。
南無阿弥陀仏