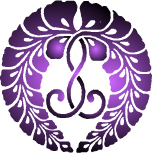涅槃会、感謝と安らぎ 「第二の矢は受けない」
涅槃会(Nirvana Day)は、約2,500年前に亡くなられたお釈迦さまを偲ぶ法要です。お釈迦さまが亡くなられたことを入滅と言い、大乗仏教の伝統では、入滅の日を2月15日としています
仏教徒はお釈迦さまの入滅を単なる悲しい出来事としてではなく、完全な悟りに至ったという意義深い出来事として受け止めています。それは、全ての苦しみから解放されることを意味し、「完全なる涅槃(Perfect Nirvana)に入る」、または、苦しみが滅した状態や世界に入る、ということで「入滅」と言います。
サンスクリット語の「涅槃(Nirvana)」は「炎が吹き消される」という意味です。この炎は、煩悩と呼ばれる私たちの欲望や執着心を象徴しています。煩悩を消し去ることで、涅槃、つまり完全な静寂と平和、そして自由の境地に至ることができます。涅槃が場所の表現をとると、浄土となり、それは「我執のない世界」を象徴しています。我執がなければ争いや苦しみもなく、平和と安らぎがあるのです。
お釈迦さまは35歳の時に涅槃に至り、ブッダとなりました。その後45年間、多くの人々に涅槃に至る道を伝え続けました。そして80歳でご入滅され、完全なる涅槃に入られました。生きているときに心は涅槃の境地に至ったのですが、肉体があるので、痛みなどの苦しみや、生きるために必要な欲がありました。そのため、完全に苦や生存欲などから解放されたのはご入滅された後でした
一部の仏教徒は、お釈迦さまも生きておられるときは、自然な人間の感情、例えば怒りを経験されただろうと考えています。けれども、お釈迦さまの怒りは恨みや憎しみに変わることはありませんでした。すぐに怒りの感情を手放すことができ、心は安らかなのです。
お釈迦さまは「私は第二の矢に射られることはない。」と言われています。「第一の矢」とは、侮辱されたり傷つけられたりしたときに反応する、最初の怒りや痛みを指します。「第二の矢」とは、その感情を引きずり、憎しみや恨みに変えることを意味します。このような感情はさらなる苦しみを生み、追加の矢で何度も射られ、さらに傷ついていくのです。
多くの人と違い、お釈迦さまは第二の矢を避けることができました。「自分」ということに執着をされないので、すぐに怒りや悲しみを手放すことができたのです。そしてお釈迦さまは、怒りを感謝の気持ちに転じられていたことが伺えるお話があります。
それはお釈迦さまが入滅された原因のお話です。弟子の鍛冶屋のチュンダが、お釈迦さまが町を訪れたと知り、食事を供養してもてなしました。ところが食後、お釈迦さまは食中毒にかかり、体調を崩されてしまいました。80歳だった御釈迦さまの体は回復せず、ご自身でも死期が近いことを理解されました。
入滅の前に、お釈迦さまはチュンダにこう語られました。
「あなたの食事が私の死の原因ではありません。私の死の原因は、この世に生まれたことにあります。自分を責めてはいけません。」
また他の弟子たちにも「チュンダを責めてはなりません。彼はとても尊い供養をしてくれました。彼の供養は、この世で私にとって最後の供養となり、そのおかげで私は完全なる涅槃に入ることができます。心から感謝しています。」と言われました。
そして、最後の教えを説かれた後、お釈迦さまは完全なる涅槃に入られた、というお話が伝わっています。
私たちは食中毒のような不快な経験をすると、つい他人を責め、怒り、恨みを持ってしまいます。しかし、涅槃に至ったお釈迦さまはチュンダを責めることなく、感謝の意を示されたのです。
私たちは仏ではなく凡夫なので、お釈迦さまのようにはできません。第三、第四、第五、、、と多くの矢を受けます。けれども、お釈迦さまにならって、できるだけ怒りを手放し、感謝の心を持つようにしてみたらいいと思います。
浄土真宗は、阿弥陀仏の力によってお浄土で涅槃を得ることができるという教えです。
親鸞聖人は浄土和讃で、「凡地にしてはさとられず、安養にいたりて証すべし」と
生きている間に、凡夫の身で涅槃を得ることはできないが、死後、お浄土に生まれ、涅槃に至ることができると言われます。浄土ではお釈迦さまと同じように完全なる涅槃を得ることができるのです。
涅槃に至るのは死後ですが、生きている間は、念仏の教えを学ぶことで涅槃の力を受け取ります。お念仏の教えは、自己中心的な考えを反省し、できるだけ我執を手放すよう促してくれます。その結果、感謝と謙虚さを持って、より平和に生きることができるのです。